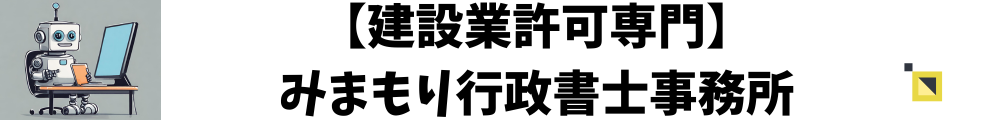公共工事入札制度について

公共工事入札制度について
1分動画解説
公共工事入札制度について
目次
1.公共工事の入札

入札とは、官公庁や地方公共団体が民間企業と契約を結ぶ際、契約相手を公平に選ぶ方法です。公共工事の入札も含まれます。
入札の種類
- 一般競争入札
- 参加資格を持つすべての民間業者が参加できる入札方式。情報は広く公開され、過去の実績がなくても参加可能です。
- 指名競争入札
- 特定の民間業者があらかじめ指名され、その業者のみが参加できる入札方式。過去の実績がないと指名されないため、まずは一般競争入札に参加し、実績を積むことが必要です。
- 随意契約(縮小傾向)
- 発注者が特定の企業を選び、直接契約を結ぶ制度です。金額が少額の場合や入札で落札者がいない場合に限定的に利用されます。
税金を財源とする公共事業では、より安価に事業を行うことが求められます。そのため、多くの業者が入札に参加し、最も安い金額を提示した業者と契約を結びます。
2.入札参加の要件

公共工事の入札に参加するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
①建設業許可を取得する
ポイント:建設業許可取得が必須
公共工事の入札に参加するには、建設業許可を取得している必要があります。
建設業許可は500万円以上の工事を行う際に必要とされていますが、公共工事ではどの規模の工事であっても取得が必須です。
ここで、公共工事の入札に参加したいから早く建設業許可がほしいというお話をいただきますが、建設業許可を取得するためには最低でも90日〜120日はかかると言われています。
早めの準備をするなどスケジューリングが重要です。
当事務所でも建設業許可の申請代行を承っておりますので、ぜひ下記からご確認ください。

② 経営事項審査(経審)の受審
ポイント:経営事項審査が必須
経営事項審査は、建設事業者の技術力や経営状況などを評価し、国や地方自治体が事業者を選別する際の指標となるものです。
経営事項審査を受けるための手続きは以下の通りです
経営事項審査の大まかな流れ
- 決算変更届の提出
- 決算終了後、まずは決算変更届を都道府県知事や国土交通省などの管轄行政庁に提出します。
- 財務諸表の送付
- 決算変更届とともに、財務諸表を経営状況分析機関に送付し、財務状況を点数化してもらいます。
- 経営規模等評価申請書の提出
- 経営状況分析結果通知書を受け取ったら、その通知書とともに経営規模等評価申請書を提出します。
この流れで経営事項審査を受けることができます。
詳細を知りたい方は過去の記事で解説しています。

③欠格要件に当てはまらないこと
公共工事の入札に参加するためには、欠格要件に該当しないことが求められます。欠格要件に該当すると入札には参加できません。主な欠格要件は以下の通りです
- 破産者で復権を得ない者
- 成年被後見人
- 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
- 民法第16条第1項に規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
- 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
- 契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
- 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者
- 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者
- 監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者
- 正当な理由がなくて契約を執行しなかった者
- 6から10までに該当する事実があった後3年を経過しない者を、契約の履行にあたり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
- 経営状況が著しく不健全であると認められる者
- 入札参加資格審査申請について虚偽の申請をし、又は重要な事実について記載しなかった者
④税金の未納がないこと
ポイント:納税状況も重要
さらに、各種税金を完納していることも前提条件です。
公共工事は税金によって賄われているため、特殊な事情で税金の支払いが免除や猶予されている場合を除き、各種税金を滞納・未納していないことが求められます。
入札参加資格の申請時に、消費税、県税、市町村民税等の完納証明書が必要となります。
3.公共工事入札の流れ
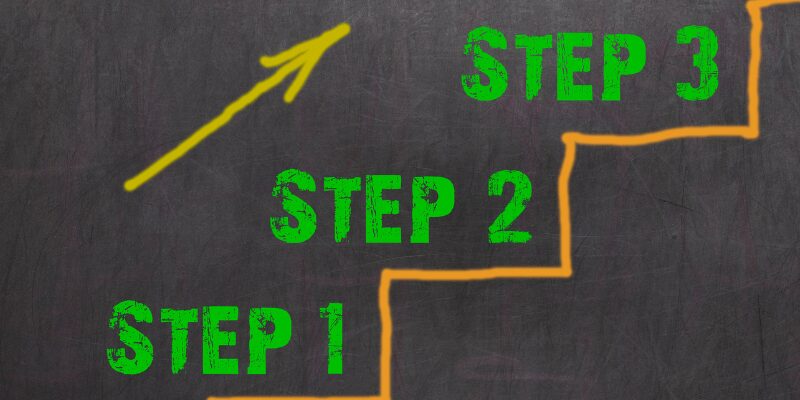
公共工事の入札に参加するための一連の流れは以下の通りです。
- 入札参加資格申請をする
- 入札案件を探す
- 入札説明会に参加する
- 案件に入札する
- 落札・契約
これらについて、順番に確認していきましょう。
①入札参加資格申請
公共工事の入札に参加するには、まず希望する国の機関や地方自治体、その他の団体に入札参加資格申請を行う必要があります。
事業者登録や指名願と呼ばれるこの申請は、入札に参加するための資格を得るためのものです。申請方法や受付時期、申請要件、資格の有効期間、必要書類は申請先によって異なります。
特に重要なのは、申請の受付時期と受付期間です。
ポイント:申請時期は1年〜2年に一度
多くの機関や自治体では、1年または2年に一度しか受け付けていないため、申請時期を逃さないよう注意が必要です。
目当ての入札案件に間に合うよう、事前に申請を行いましょう。
入札参加資格申請には通常、申請料は発生しませんが、案件の業務内容によっては、追加で認証や資格、実績が求められる場合があります。例えば、ISO規格の認証や測量士、一級建築士の免許などが必要です。
入札参加資格申請に関する情報は、希望する自治体や国の機関のホームページで常に確認しておくと良いでしょう。
②入札案件を探す
入札参加資格を取得した後は、自社に適した入札案件を見つける必要があります。以下の方法で案件情報を収集しましょう。
- 入札情報サイトの利用
- 入札情報サイトを活用することで、広範な案件情報を効率的に収集できます。サイトの利用には費用がかかる場合がありますが、情報の漏れが少なく、迅速に案件を把握できます。
- 行政機関の公式サイトをチェック
- 参加したい行政機関のWebサイトで、公告された入札案件を確認します。
③入札説明会に参加する
案件情報を確認し、入札参加を決めたら、次に仕様書を取得します。仕様書には案件の背景や目的、入札方式、要件などが記載されています。
仕様書は発注機関のWebサイトから取得できる場合も増えており、事前に確認しておくと便利です。仕様書の受け取りには説明会への参加が必要なこともあります。
仕様書に不明点があれば、発注機関の担当窓口に問い合わせることが重要です。質問には提出期限があるため、説明書をよく確認し、期限内に対応しましょう。
④入札する
入札に参加するには、必要書類を揃える必要があります。
書類の種類は行政機関や入札案件によって異なるため、事前に確認しておくことが重要です。
ポイント:最低制限価格を下回らないように
最低制限価格というラインを下回ると失格となりますし、価格を過度に下げると利益が出ない可能性もあります。正確な見積もりを基に、適正な入札価格を設定することが重要です。
⑤落札・契約
官公庁の「一般競争入札」では、最低金額で入札した事業者が落札します。自社が落札した場合は、発注機関との契約を進めます。
落札結果と参加事業者の入札金額は、通常、発注機関のWebサイトで公開されます。
4.まとめ
以上、公共工事入札制度について解説しました。
建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です

5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば

長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
当事務所であれば

30年間アフターサービスの対応が可能です!
詳しくは下記の記事をご覧ください!
お問い合わせは下記から
お気軽にお問い合わせください。092−725−2275受付時間 8:00-20:00 [土日祝対応可]
お問い合わせ