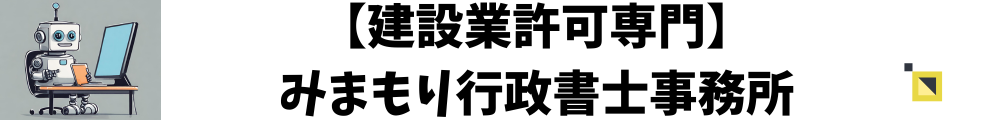建設工事を請負う時、契約書を作成していますか?

建設工事を請負う時、契約書を作成していますか?
目次
1.対等な立場で適正な契約を結ぶ必要があります

建設工事の請負契約は、本来、その契約の当事者の合意によって成立するものですが、合意内容に不明確、不正確な点がある場合、その解釈規範としての民法の請負契約の規定も不十分であるため、後日の紛争の原因ともなりかねません。
また、建設工事の請負契約を締結する当事者間の力関係が一方的であることにより、契約条件が一方にだけ有利に定められてしまいやすいという、いわゆる請負契約の片務性の問題が生じ、建設業の健全な発展と建設工事の施工の適正化を妨げるおそれもあります。
そうならないように、建設業法では下記のように対等な立場において、公正な契約を締結することを定めています
第十八条 建設工事の請負契約の原則
e-GOV法令検索
建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。
ポイント:契約書を交わす必要がある
公正な契約を結ぶために、請負契約の当事者は契約書を交わす必要があります。次項で詳しく解説します。
2.契約書を交わさなければなりません

①建設業法第19条に記載があります
建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期、請負代金の支払時期方法等下記の事項を記載した契約書を取り交わさなければなりません。(法第19条)
第十九条 建設工事の請負契約の内容
e-GOV法令検索
建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一 工事内容
(後述するため以下省略)
2 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
3 建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。
ポイント:電子契約でもOK
相手型の承諾を得るなど、一定の要件を満たせば、書面契約に代えて、電子契約による締結も認められています
②契約書に記載が必要な内容

契約書に記載が必要な内容
- 工事内容
- 請負代金の額
- 工事着手・完成時期
- 工事を施工しない日又は時間帯の定めの内容
- 前払金・出来高払の時期及び、方法
- 一方からの申出による設計変更又は工事中止の場合における工期又は代金の変更、損害の負担及びそれらの算定方法
- 天災その他不可抗力による工期の変更、損害の負担及びその額の算定方法
- 価格変動等による請負代金又は工事内容の変更
- 工事施工により第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担
- 注文者が資材提供又は機械貸与するときの内容及び方法
- 注文者の完了検査の時期及び方法、引渡しの時期
- 完成後の請負代金の支払時期及び方法
- 工事の目的物の瑕疵担保責任又は保証保険契約の締結その他の措置の内容
- 履行遅滞、債務不履行の場合の遅延利息、違約金、その他の損害金
- 契約に関する紛争の解決方法
- その他国土交通省令で定める事項
③いつ交わす必要があるのか
工事請負契約書が締結する必要があるのは、以下の工事の受発注が行われるタイミングです
- 新築工事
- 増改築工事
- 改装工事
- 外構の整備工事など
ポイント:着工前に交わすことが必要
また、契約書面の交付については、災害時等でやむを得ない場合を除き、原則として工事の着工前に行う必要があります。(国土交通省「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第3版)」8頁に記載あり)
④契約を交わす上での注意点

ポイント:適正な工期を設定する
第十九条の五 著しく短い工期の禁止
e-GOV法令検索
注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。
建設工事の請負契約に基づき、受注者が適正な施工を行うためには、施工内容に応じた適正な工期設定が必要です。
ポイント:不当に低い請負代金を設定してはNG
第十九条の三 不当に低い請負代金の禁止
e-GOV法令検索
注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を受注者と締結することを禁止しています。
発注者が、取引上の地位を不当に利用して、不当に低い請負代金による契約を強いた場合に、受注者が工事の施工方法、工程等について技術的に無理な手段、期間等の採用を強いられることとなり、手抜き工事、不良工事や公衆災害、労働災害等の発生につながる可能性もあるため、禁止しています。
ポイント:不当な使用資材の指定はNG
第十九条の四 不当な使用資材等の購入強制の禁止
e-GOV法令検索
注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。
この「不当な使用資材等の購入強制」が禁止されるのは、請負契約の締結後における行為に限られます。
発注者の希望するものを作るのが建設工事の請負契約であり、請負契約の締結に当たって、発注者が、自己の希望する資材等
やその購入先を指定することは、当然想定し得るためです。
3.契約書を交わさなかった場合の罰則は

ポイント:営業停止や許可取り消しの可能性もあり
もし工事請負契約書を作成しなかった場合、建設業法違反となり、国土交通大臣または都道府県知事から指示を受ける可能性があります(同法第28条第1項)。
さらに、指示に従わなければ営業停止処分となることがあり(同条第3項)、特に悪質な場合には建設業の許可が取り消されることもあります(同法第29条第1項第8号)。
また、これらの行政処分を受けると、事業者の商号や違反内容が公表されるため、社会的な信用の低下も懸念されます。
建設業者は建設業法の規定を遵守し、適正に工事請負契約書を締結することが重要です。
4.まとめ
以上、請負契約における契約書の必要性について解説しました。
建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です

5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば

長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
当事務所であれば

30年間アフターサービスの対応が可能です!
詳しくは下記の記事をご覧ください!
お問い合わせは下記から
お気軽にお問い合わせください。092−725−2275受付時間 8:00-20:00 [土日祝対応可]
お問い合わせ