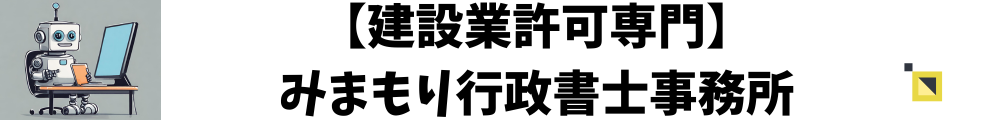【個人事業主から法人へ】建設業許可の承継はできる?

【個人事業主から法人へ】建設業許可の承継はできる?
目次
1分動画解説
建設業の承継ってできる?
1.建設業許可は承継できるのか?

ポイント:結論から言うと可能
特に、個人事業主に取得した建設業許可を法人成りする際に、そのまま承継したいと考えている方には、許可承継できるかは非常に重要なことではないでしょうか。
建設業許可を承継することは結論から言うと可能です。
法人成りする際に、許可を取得する方法は大きく2種類あります。
法人成りの際に許可を取得する方法
- 建設業許可を新たに取り直す
- 法人に許可を承継する
それぞれの手続きには異なる要件や流れがあるため、特徴を理解したうえで事前にどちらの方法を選択するか決めておくことが重要です。
どちらの方法を選ぶ場合でも、「必要書類が多い」「許可取得までのスケジュール管理が厳密に求められる」 という点から、手続きは比較的複雑になります。
2.法人成りする際に許可を取得する方法

①建設業許可を新たに取り直す方法
従来からあるこの方法は、建設業許可を承継するかというとそうではありません。
なぜなら、個人事業を廃止した上で、新たに法人で許可を取り直す方法だからです。
新規の許可が下りてから、個人事業主の許可を廃業すれば良いのではないかと考える人もいるかもしれません。
ですが、建設業許可では、会社に常勤している専任技術者や常勤役員(経管)の設置が要件となっています。
ポイント:兼務では常勤性が認められない
そのため、個人事業主と法人で専任技術者や常勤役員(経管)の役割を兼務している場合、どちらにも常勤しているとは認められないため注意が必要です。
つまり、必ず「個人事業主の廃業 → 新規法人の建設業許可」の取得という流れになるということです。
厳密にいうと、廃業と法人での許可の取得の手続き自体は同時に進めます。
ポイント:1ヶ月〜2ヶ月程度無許可期間がある
新規で許可を取得するまでには、許可行政庁による審査に約1か月程度かかります。そのため、個人事業主を廃業してから法人で新たに許可を取得するまでの間は、建設業許可を持たない無許可の状態になってしまいますので注意が必要です。
この無許可期間中は、500万円以上(建築一式工事では1,500万円以上)の工事を請け負うことができません。万が一、許可を受けずにこれらの工事を請け負うと、建設業法違反となるため注意が必要です。
法人で許可を取り直す場合は、無許可期間が生じることを十分に理解し、事前に対応を検討しておきましょう。
②法人に許可を承継する方法
個人事業での許可を廃止せずに法人に引き継ぐ方法です。
令和2年10月に新設された制度法改正で新たにできるようになった手続きです。
ポイント:事前に許可行政庁との相談が必要
個人から法人へ許可を承継する場合、事前に許可行政庁と打ち合わせが必要です。
この承継手続きでは、承継の事実が発生する前に認可を受ける必要があるため、事前確認が欠かせません。多くの許可行政庁が発行する手引きにも、「事前に相談してください」と記載されていることがほとんどです。
これは福岡県でも同様で、建設業許可の手引きにも記載があります
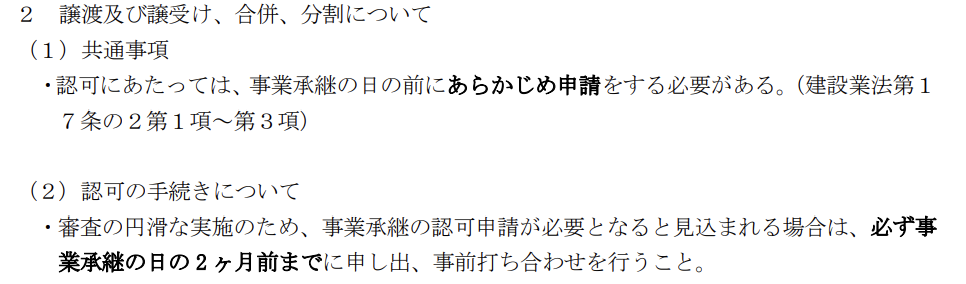
また、承継には特有の必要書類や細かな要件があるため、スムーズに手続きを進めるためにも、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。
次項で許可の承継をするにあたっての注意点を見ていきましょう
3.許可の承継をする際の注意点

①譲受人は許可要件を満たせるか確認する
事業譲渡により建設業許可を承継する場合、まず初めに「事業譲渡が成立した時点で譲受人が建設業許可の要件を満たしているか」を確認する必要があります。
要件の内容は通常の建設業許可と同様で、以下の通りです。
- 欠格要件に該当しない・誠実性があること
- 営業所に独立性があること
- 財産的基礎を有していること
- 社会保険に加入していること
- 専任技術者が在籍していること
- 常勤役員等が在籍していること
②全ての許可業種が承継される
建設業許可の承継においては、許可を受けているすべての業種が一括で承継されます。
一部の許可業種のみを承継することは認められていません。また、承継と同時に新たな業種を追加することもできないので注意が必要です。
例えば
譲渡人が土木施工管理技士を専任技術者として土木一式と水道施設工事業の許可を受けているが、譲受人には建設機械施工技士しか専任技術者になれる人がいない場合、水道施設工事業の許可要件を満たすことができません。
ポイント:承継できない業種は譲渡人が廃業しておく
上記の例の場合、許可要件を満たしていない水道施設工事業だけでなく土木一式も含めて許可の承継が認められません。
このようなケースでは、事業譲渡前に譲渡人側で水道施設工事業を廃業し、土木一式の許可だけを受けている状態にしておくことが現実的な対策となります。
個人事業主から法人成りの場合には、専任技術者や常勤役員(経管)が変わることは考えづらいですが、取得したすべての業種が引き継がれることを頭に入れておく必要があります。
②譲渡人に届出未提出がないことが条件
ポイント:決算変更手続きなど提出しておく必要あり
建設業許可を受けた事業者は、その許可行政庁に対して、年に一度の事業年度終了報告(決算変更届)をはじめ、商号、所在地、役員、資本金など、建設業法で義務付けられている届出を漏れなく提出している状態でなければ、許可の承継は認められません。
③事前の認可を受ける必要がある
許可の承継は事前の認可制であり、法文にも「あらかじめ」と明記されています。この制度により、事前の認可を受けることで建設業の許可を承継することが可能になります。
事業譲渡全体のスケジュールを把握し、事業譲渡の効力発生日から逆算して余裕をもって認可申請の準備を進めましょう。
④引き続き使用できる許可番号について
使用できる許可番号
- 建設業許可業者が無許可業者に承継される場合
- 従前の許可番号が引き継がれます。
- 複数の建設業許可業者間で承継が行われる場合
- 引き継ぐ許可番号の選択が可能です。
⑤認可後の許可の有効期間
事業譲渡当日から許可は有効です。
許可の有効期間は事業譲渡の日の翌日から5年間となります。
⑥福岡県の場合は下記内容を確認
※個人事業主が法人成り後の法人の 1 人代表取締役となる場合、法人の口座開設・税務署への法人設立届出以外の法人側としての職務が全く発生しないという根拠は乏しく、現在許可の建設業に係る職務(経管・専技等)があるため 2 人以上(個人事業主以外が代表取締役)の役員を設置すること。
なお、諸事情により個人事業主が法人成り後の 1 人代表取締役として申請する場合は、認可申請書受理と同時に廃業届(法人設立日で廃業日記入)を提出すること。これをもって、許可要件の不足により認可ができない場合の本県の備えとする。
福岡県建設業許可の手引きp154
なお、認可処分を行えた場合は、認可通知交付時に廃業届は必ず返却します。
原則、個人事業主時代に経管と専技の条件を事業主本人が満たしている場合には、法人の役員を2人以上配置する必要があります。
諸事情により、事業主本人が代表取締役とならざるを得ない場合には、認可申請書と、同時に事業主の廃業届を提出する必要があります。
4.まとめ
以上、個人事業主から法人成りする場合の事業承継について解説いたしました。
建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です

5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば

長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
当事務所であれば

30年間アフターサービスの対応が可能です!
詳しくは下記の記事をご覧ください!
お問い合わせは下記から
お気軽にお問い合わせください。092−725−2275受付時間 8:00-20:00 [土日祝対応可]
お問い合わせ