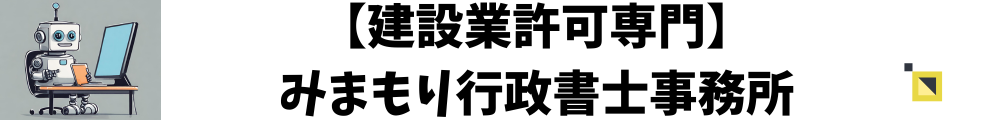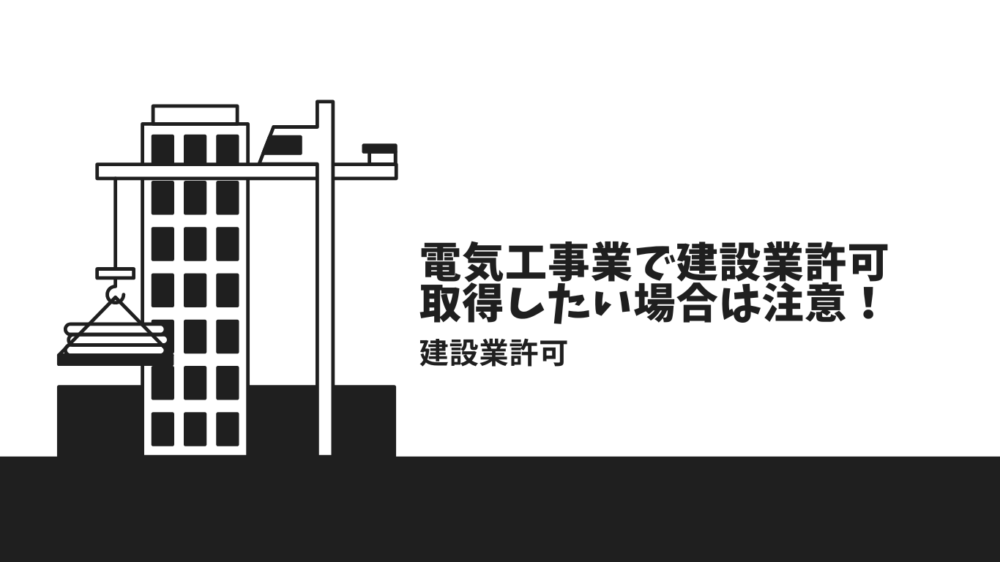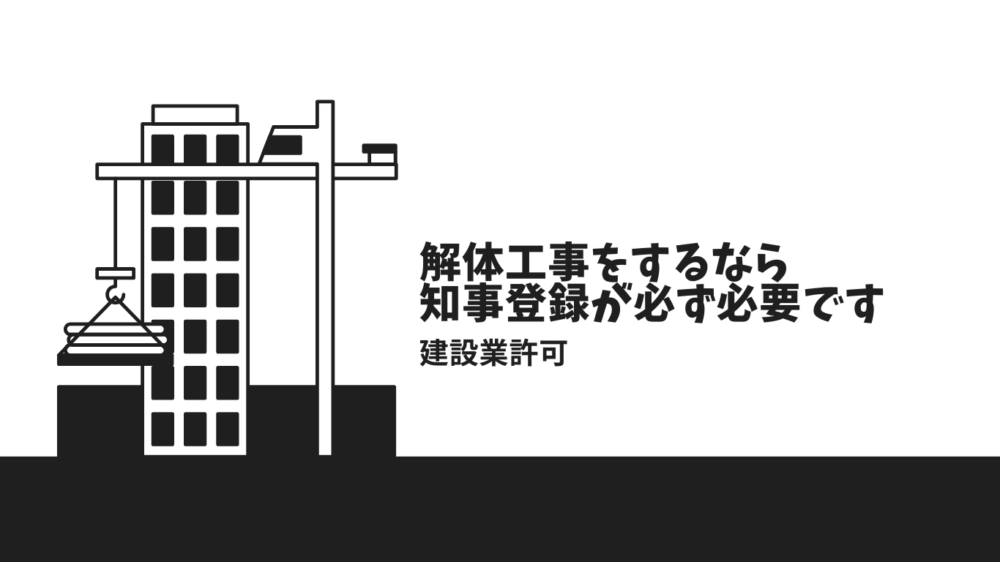建設業許可とは

建設業許可とは?
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
国土交通省H Pより
このように、建設工事を請け負う際には、原則、建設業許可を受けなければならないと、法律で決まっています。
これから建設業許可の取得を考えている事業者様にとって、まずは建設業許可がどのようなものなのかを知りたい方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、建設業許可の制度の基本知識をざっくりと解説しています。
まずはどんな制度なのか理解していただけるようになっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
建設業許可制度について
ざっくりと理解できます
目次
1分動画解説
建設業許可とは(前編)
建設業許可とは(後編)
1.建設業許可は必ず取得が必要なのか?
ポイント:「軽微な工事」のみを事業とする場合には建設業許可は不要
そもそも建設業許可は、建設業を事業にする事業者が必ず取得しないといけないわけではありません。
軽微な工事のみを行う場合には建設業許可を取得する必要はないのです。
軽微な建設工事とは下記のとおりです。
軽微な建設工事とは
- 建築一式工事にあっては、1,500万円に満たない工事
- 建築一式工事にあっては、延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
- 建築一式工事以外の建設工事にあっては、500万円に満たない工事
【注意点】
- 2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額(同令第1条の2第2項)
- 注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含む額(同令同条第3項)
- 単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
- 消費税及び地方消費税を含む額
ポイント:電気工事と解体工事業者は注意
ただし、原則あるところに例外ありで、電気工事と解体工事に関しては建設業許可とは別に登録や許可が必要です。
詳しくは過去の記事で解説していますので下記からご覧ください。
ですので、ご自身の事業で税込500万円以上(一式工事の場合は1500万円)を超えそうな時に初めて建設業許可を取得することを検討されたら良いでしょう。
ポイント:税込500万円未満の工事は原則許可不要
500万円未満(一式工事の場合は1500万円未満)の工事のみを行うだけの事業者は原則許可が不要です。
つまり、500万円未満(一式工事の場合は1500万円未満)の工事であればどの業種の業務も原則行って良いということになります。
だだし請負金額が500万円未満でも違反になることがあります。
過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください。
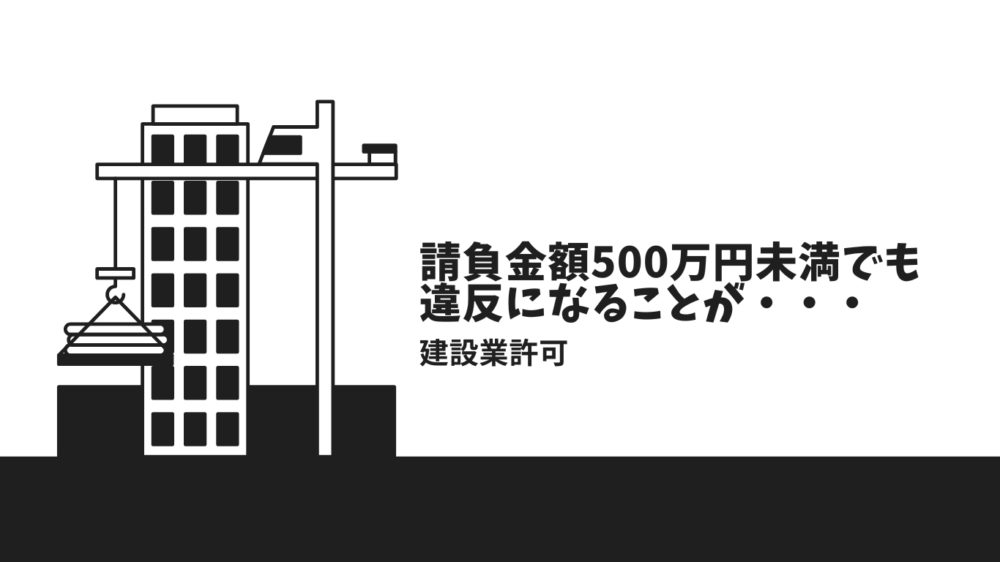
2.建設業とは
①建設業の種類

ポイント:「建設業」とは、29業種に分かれている
「建設業」とは、建設工事(29業種(※))の完成を請け負う営業をいいます。
29業種とは
※建設業の許可は、2業種の「一式工事業」と27業種の「専門工事業」の29業種ごとに分けて行われ、業種ごとに取得することとなります。
土木一式工事、建築一式工事、大工、左官、とび・土工、石、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、舗装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体(※)
※「一式工事」とは、総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であり、原則として、大規模又は施工内容が複雑な工事を、元請業者の立場で総合的にマネージメントする事業者向けの許可となります。「一式工事」の許可のみを受けている者が、「専門工事」を単独で請け負う場合には専門工事の許可が必要となります。
これらはいわゆる建設業許可の中の業種を表しています。
工事といっても施工内容によって、必要な知識・技術・経験というのは全く異なります。
例えば、整地や樹木の植栽をする「造園工事」と工作物を解体する「解体工事」というのは全く違いますよね?
これらは同じ建設業ではあるものの、必要な知識や技術など変わってきます。
そのため、適切に施工体制を確保できるよう、建設業法で工事を29種類に細分化しているということになります。
ポイント:取得したい業種を選択する必要がある
つまり、建設業許可を取得したい事業所様は、これらの29種類のうちから、自社で施工したい工事が何に該当するのか選択する必要があります。
例えば
- 解体工事を専門としている事業者
- 「解体工事業」
- ネットワーク設備やWi-Fi工事など専門としている事業者
- 「電気通信工事業」
- 外構などの工事を専門としている事業者
- 「造園工事業」
など、業種を選択しましょう。
②業種は複数取得することが可能
また、建設業の許可は業種ごとに取得する必要がありますが、取得する業種は複数でも問題ありません。
例えば、冷暖房の工事である「管工事」とWi-Fi工事などの「電気通信業」を事業として行っているのであれば、同時に2種類の業種の建設業許可を取得できますし、「管工事」と「電気通信業」の工事を請け負う場合には、税込500万円以上の工事を請け負うことが可能です。
逆にいうと上記の場合には、「管工事」と「電気通信業」以外の業種では500万円以上の工事を請け負うことができません。
3.建設業許可の要件

ポイント:許可要件をクリアする必要がある
建設業許可は誰でも取得できるものではありません。
建設業法は
- 建設工事の適正な施工を確保
- 発注者の保護
- 建設業の健全な発達を促進
を目的としており、これらの目的を達成できるものしか、建設業許可は取得できません。その要件とは下記のとおりです。
建設業許可を取得するために必要な6つの要件
- 誠実性を有すること、欠格要件に該当しないこと
- 主たる営業所があること
- 財産的基礎又は金銭的信用を有すること
- 適正な社会保険に加入していること
- 営業所ごとに専任技術者を置いていること
- 経営業務の管理責任者としての経験を有する者を置いていること
これらの許可要件の詳細を確認したい方は下記からご覧ください。
4.許可の有効期間は?

ポイント:許可の有効期間は5年間
建設業の許可の有効期間は、5年間です。
このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
5.無許可営業の罰則は?
無許可営業の典型的なケースは、建設業許可を受けずに「軽微な工事」を超える工事や請負工事を行うことです。
また、下請業者が許可を持たない状態で、軽微な工事の範囲を超える下請契約を締結する場合も無許可営業に該当します。
この場合、下請業者だけでなく元請業者も責任を負います。
元請業者は、下請業者が許可を持っているかどうかを確認し、許可を持たない業者に工事を依頼した場合、監督責任を問われることがあります。
これらの行為は建設業法違反となり、建設業法第47条に基づいて罰則が科されます。
第四十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、「三年以下の懲役または三百万円以下の罰金」に処する。e-GOV法令検索より
建設業法違反が認められた場合、関与者は3年以下の懲役や300万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、「情状により、懲役および罰金を併科」とあるため、状況によっては懲役と罰金の両方が課せられることもあります。
さらに、刑事裁判において逮捕・送検され、被告人として刑事裁判にかけられる可能性もあります。
懲役や罰金刑が確定した場合、建設業許可が取り消され、その後5年間は再度建設業許可を取得することができなくなることも考えられます。
6.まとめ
以上、建設業許可の概要について、ざっくりと説明させていただきました。
建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です

5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば

長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
当事務所であれば

30年間アフターサービスの対応が可能です!
詳しくは下記の記事をご覧ください!
お問い合わせは下記から
お気軽にお問い合わせください。092−725−2275受付時間 8:00-20:00 [土日祝対応可]
お問い合わせ