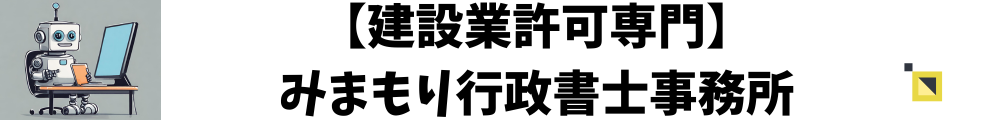法人設立と建設業許可取得はどちらが先が良い?

法人設立と建設業許可取得はどちらが先が良い?
目次
1.法人設立と建設業許可はどちらが先の方が良いのか

ポイント:一般的には法人化を先にすることをお勧め
建設業許可の取得を考えている個人事業主の方の中には、法人成りすべきかどうか迷うケースも少なくありません。
基本的には、許可申請を行う際に、あらかじめ法人化しておく方がスムーズです。
なぜなら、個人事業主として許可を取得した場合、後に法人化する際に再び建設業許可を取り直したり、承継の手続きをする必要があり、結果として手続きの負担が増えてしまうためです。
法人成りに際しての、許可の新規取得と許可の承継に関しては過去の記事で詳しく解説していますので、下記からご確認ください。

今回の記事では法人設立してから、建設業許可を申請するという前提で、法人設立時の重要なポイントを解説していきます。
2.建設業許可を取得するための法人設立のポイント

①定款目的に工事業種を明記
ポイント:定款目的に許可取得しようとしている業種の工事を記載する
会社設立時に作成する定款には、事業目的を明記しなければなりません。この事業目的は登記事項として、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)にも記載されることになります。
法人で建設業許可を申請する際には、この事業目的に許可を取得したい工事業種が含まれている必要があります。
例えば、「タイル・ブロック・レンガ工事業」の許可を取得したい場合、定款の事業目的欄に「タイル工事業」「レンガ工事業」などと明記しておく必要があります。
事業目的に対象業種が含まれていない場合、後から目的変更の登記が必要になる可能性があるため、会社設立時に忘れずに記載しておきましょう。
「建設業法に基づく建設業」や「建築・土木工事の請負及び施工」というように記載しておくと、すべての業種を網羅することができるので、無難な対応といえます。
②経営業務の管理責任者は役員として登記する
建設業許可を取得するには、「経営業務の管理責任者がいること」が必須条件の一つです。
この要件を満たすには、許可を受ける工事業種に関して、会社の役員または個人事業主として5年以上の経験がある者を最低1名、会社の役員として登記する必要があります。
通常、社長自身が経営業務の管理責任者を務めることが多いですが、要件を満たしていれば社長以外の役員でもなることが可能です。
ポイント:息子などの後継者を役員登記しておく
また、将来を見据えて後継者候補を役員として登記しておくのも一つの選択肢です。
役員経験を積ませておけば、5年には経営業務の管理責任者としての資格を得られるため、事業継承をスムーズに進めることができます。
③営業所ごとに専任技術者がいるかを確認する
ポイント:営業所ごとに必要な専任技術者
建設業許可を取得するためには、営業所ごとに専任技術者を配置することも求められます。
専任技術者になれるのは、以下のいずれかの条件を満たす人です。
専任技術者のざっくり要件
- 指定の国家資格を保有している
- 一定の実務経験を有している
また、専任技術者は下記のようなルールがあります。
専任技術者の基本事項
- 営業所ごとに配置
- 営業所が複数ある場合、それぞれの営業所に1人以上、専任技術者を配置する必要があります。
- 常勤性の要件
- 専任技術者は常勤である必要があり、その常勤性を証明する書類が求められます。
- 兼務不可
- 他の会社の職員や他の営業所の専任技術者を兼務することはできません。
上記のように、営業所が複数ある場合、それぞれの営業所に専任技術者を置かなければなりません。
そのため、建設業許可の専任技術者要件を満たせるように、計画を立てておくことが重要です。
なお、専任技術者は経営業務の管理責任者と兼務することができますが、役員として登記する必要はありません。
④設立時の資本金に注意
ポイント:資本金の要件を満たせるようにしておく
建設業許可を取得するには、「財産的基礎または金銭的信用を有していること」が条件の一つです。
具体的には、以下の資本金額が必要になります。
財産的基礎要件
- 一般建設業許可
- 資本金500万円以上(または500万円以上の預金残高など)
- 特定建設業許可
- 資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上(加えて、流動比率75%以上、欠損比率20%以下)
一般建設業許可を取得する場合は、資本金500万円以上を設定しておけば問題ありませんが、特定建設業許可を取得する場合は注意が必要です。
特に設立初年度から特定建設業許可を取得する場合、資本金2,000万円では不十分です。自己資本4,000万円以上という条件も満たす必要があるため、資本金4,000万円以上で設立する必要があります。
また、資本金が3,000万円を超えると、一部の税制優遇(中小企業投資促進税制の税額控除など)が適用されなくなる点にも注意が必要です。税制優遇を考慮する場合は、資本金を3,000万円以下に設定し、不足分の自己資本は利益の積み重ねで補う方法も検討しましょう。
3.まとめ
以上、法人化と建設業許可取得どちらが先が良いか解説しました。法人化は当事務所でも承っております。
建設業許可を新規で取得しようと考えている方
建設業許可は取得した後の
フォローが重要です

5年ごとの更新手続き・毎年の決算変更届の提出
必ず行わなければなりません
一生、建設業をやるのであれば

長く付き合いができる
行政書士を選ぶべきです
当事務所であれば

30年間アフターサービスの対応が可能です!
詳しくは下記の記事をご覧ください!
お問い合わせは下記から
お気軽にお問い合わせください。092−725−2275受付時間 8:00-20:00 [土日祝対応可]
お問い合わせ